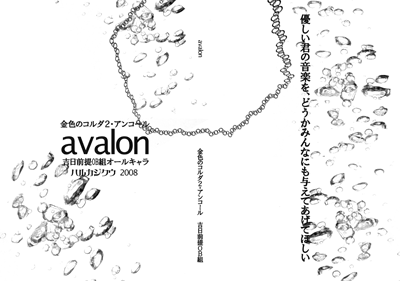「avalon」(A5/96p/オンデマンド/頒布価格800円)
夏コミ発行予定の新刊です。
アンコール設定の吉日前提のOB本です。
三章からなっていまして、
「金澤コンクール編」「王崎コンクール編」「日野コンミス編」(←このパートが一応吉日です)
他の二つのパートは友情ものです。
メインは、金澤、吉羅暁彦、吉羅美夜、王崎、都築、日野そしてリリ。
現役では月森と天羽さんに出番があります。
他の現役生は名前が会話に出てくるだけ、みたいな感じです。
過去のコンクールの設定や、美夜さんの性格などは、そうとう捏造していますので、ご注意ください。
当然のことながらですが、美夜さんの死にネタがあります。
吉日パートは糖度低め。
夏コミでは、
8月16日(二日目・土) 東6ホール ソ-26a 「まんねんろう」さん(コルダ・火海)に委託していただくことになりました。
三日目西のハルカジクウスペには搬入ありません。ご注意ください。
通販はコミケ終って落ち着きましたら。
第一章 金澤と吉羅
暁彦が「優勝できない」と言ったのは、姉の美夜がいるからだろう。
暁彦のヴァイオリンも才能の豊かさを感じさせたが、美夜のヴァイオリンは完成度でそれを上回っていた。
「まあ、優勝を目指すつもりで取り組んではいますが。他の先輩方もなかなかのものですし。もちろん金澤先輩も」
「おっ、嬉しいね、そんなふうに言ってくれるとは」
ちゃかすように言った金澤に、暁彦はあからさまに溜息をついた。
「あなたって人は……」
その時、階段から続くドアが開いた。
そして、姿を見せたのは、ヴァイオリンケースと通学鞄を持った吉羅美夜だった。
お姫様のお出ましだ。
金澤は心の中でそう思った。
あれはなんのオペラのヴィデオだっただろう。図書室の視聴ブースでみたあの舞台。
タイトルがなぜかでてこない。
舞台の奥から麗しいソプラノを響かせて登場したプリンセス役のマドンナ。その可憐さが舞台をあっという間に満たしていった。
今の美夜の登場はそのシーンを彷彿とさせた。
「おまたせ、暁彦。あら、金澤君も一緒だったの?」
美夜が近づいてきた。暁彦は、美夜の練習が終るのを待っていたのだ。それに金澤が付き合っていた。
「うん、ま、暇だったからさ」
「余裕なのね」
金澤の言葉に、美夜が笑顔で言った。
「俺は、喉は酷使しないの。なにしろ替えがないからさ」
「そうね……そういう意味では声楽は大変だと思うわ」
「体調管理も演奏者の技術の一つですからね。……姉さん、疲れてない?」
暁彦が、姉の鞄を持とうと手を出した。
美夜もそれにしたがって、自分の鞄を簡単に手渡した。慣れた仕草だった。暁彦は自分の足元に置いてあった鞄とヴァイオリンケースも持った。
「大丈夫よ」
「じゃあ、帰ろうか。……では先輩、また明日」
「おう」
金澤が軽く手をあげた。美夜が尋ねる。
「金澤君はまだ帰らないの?」
「俺はもうちょっと、空でもみていくわ。ははは、ロマンティックすぎるか?」
「ううん、素敵」
美夜が笑って首を振った。
第二章 王崎と都築
『じゃあ、次はモーツァルトがいいのだ!』
「はいはい、リリは人使いが荒いのね」
そういいながらも、都築は鍵盤を叩き始めた。
講堂に響く軽やかなメロディ。
それは明後日は、第一セレクションという日だった。
王崎信武は講堂へ、音の響きを確かめにきていた。
音楽科の生徒といえども、講堂で弾く機会はあまりない。セレクションを控えて、響きを確かめるのは、大事なことだった。
ヴァイオリンケースを抱えて、講堂のドアを静かにあけると、先客がいた。
ステージ上のピアノに向かっている都築茉莉、そして、その上空を飛び回るファータのリリ。
ファータの姿を見るのは、最近ようやっと慣れてきた。
リリは、都築に好きな曲をリクエストしているようだった。
メロディに合わせて、リリは楽しそうに羽を瞬かせている。
曲が終った。
『ありがとうなのだ! では、我輩はこれで!』
きらりと一瞬リリが纏う光が強くなったかと思うと、次の瞬間にその姿は消えていた。
「あら」
舞台近くの前方のドアの傍にいた王崎に都築は気がついた。
「次、王崎君が使うのね。ごめんなさい、今、あけるわ」
「ああ、いや、急がなくていいよ」
王崎もステージ上にあがった。
「今のは、ファータのリリ?」
「ええ。けっこうリクエストが多いのよ、彼」
「……都築さん、弾いてあげてるの?」
と、王崎は彼女に尋ねた。
都築は、え?という顔をした後、うなずいた。
「ええ」
なんてことないというふうに都築茉莉は言った。
「喜んでくれるのよ」
都築はすこし笑った。
第三章 香穂子と暁彦
「まだ夕食には早い時間だが……どこかに寄ろうか」
星奏学院の地をあとにして、三つ目の信号で赤信号にひっかかった時に吉羅がそういった。
一応、疑問系になっているようにも聞えなくもない「寄ろうか」だが、淡々と喋る吉羅の言葉はいつも大きな抑揚はないので、それは断定しているように聞えた。
だけどそれで香穂子はよかった。
「はい。実は練習でお腹がすいています」
正直に言った。もう吉羅と食事にいくのも何度目か。このくらいのことは普通に話せる。
「では、いこう」
信号が青に変る。車は再び走り出した。
「ピアノの土浦君の書類が受理されたよ」
早めの時間だったせいか、そのイタリアンレストランは空いていた。
いつも立ち寄る港湾スクエアのレストランだった。ここは吉羅が気にいってる場所のひとつで、理由は「外車の駐車が断られない」ことが大きいそうだ。
確かに、外と地下にある駐車場はとても広かった。週末の昼間は家族連れで賑わうのだろう。
「そうですか」
香穂子は、すこし視線を落とした。テーブルはすでにドルチェも終って、コーヒーだけが残っている。
吉羅が言っているのは、土浦梁太郎の普通科から音楽科への転科の事務手続きが終ったということだった。詳しく説明されなくても、香穂子には判っていた。もうすぐ三学期も終る。つまり、二年生が終る。土浦の転科手続きがされる時期だろう。
吉羅が言った。
「音楽科の二年生は、一人減るけども、一人増える。生徒数は変らないわけだ」
減るひとりは、月森蓮のことだろう。彼は春からウィーンへの留学が決まっていた。
「……寂しくなります」
「どちらが?」
「それはどっちもです。月森君は海外で、土浦君は別の校舎になっちゃうし」
それは正直な心境だった。春の学内コンクールで、香穂子と同じ学年の二人は、それぞれ次の春からは新しい道に進んでいく。
二人とはコンクールで知り合って親しくなったので、付き合いの長さでいえば、短い。
だが、三人の間には、ただの同級生とは違うような絆があるような気がしている。
私の勝手な思い込みかしら? と香穂子はたまに思うこともあるが、土浦君と月森君は仲が悪いようでいて、どこか認めあってる感じもするし……と香穂子は思っている。
「コンクール参加者同士は、他の生徒たちとは違う何かがあるような気がするからね」
そう言う吉羅も、星奏学院に在籍していた時はコンクール参加者だった。
(本文より抜粋)